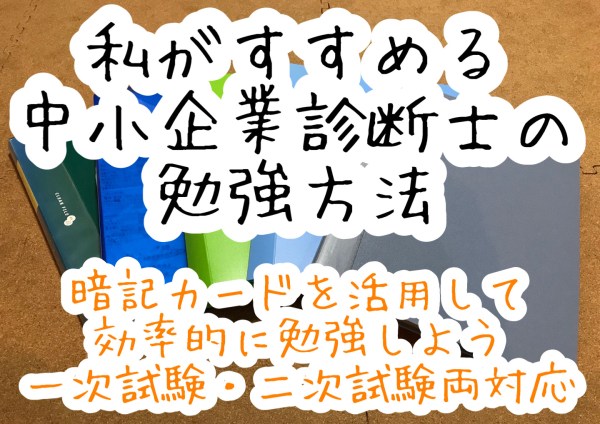こんにちは!中小企業診断士試験のカズユキです。
今回は貸借対照表のルールについて解説します。
前回までは2回にわたって貸借対照表の内容についてかいつまんで解説しました。
概要と資産の部については下のリンクをどうぞ
負債の部と純資産の部について下のリンクから見てください
流動と固定の分類は
資産の部には「流動資産」と「固定資産」があり、負債の部には「流動負債」と「固定負債」があります。
この分類をするはどのような基準で行われるでしょうか?
流動と固定を判別する基準は2段階あります。
- まずは「正常営業循環基準」で判断する
- 判断できない場合は「一年基準」で判断する
これらを解説していきます。
正常営業循環基準
正常営業循環基準というのは「通常の営業活動で生じる資産や負債については、流動に分類するルール」ということです。
通常の営業活動とは具体的にどういったことでしょうか?
例を挙げると、
- 製造目的で材料を仕入れる
- 製品を生産する
- 商品を販売する
といった感じです。
流通業者であれば、
- 商品を仕入れる
- 商品を販売する
といった流れですね。
これを基準に考えた場合
- 商品を販売した売上債権(受取手形・売掛金)
- 材料や商品を仕入れた仕入債務(支払手形・買掛金)
- 棚卸資産(商品・製品・仕掛品・原材料)
これらが流動資産(流動負債)に分類されます。
逆に工場建設や生産設備導入など長期的なスパンのものは通常の営業活動とはみなしません。
一年基準(ワン・イヤー・ルール)
一年基準とは「先ほどの正常営業循環基準に該当しない資産・負債については、決算日から一年以内に決算期日が到来するものは流動資産に分類する」といったものです。
一年基準なので「ワン・イヤー・ルール」と言います。
まずは「正常営業循環基準」で流動・固定の分類を行いますが、これで判断ができない場合は「一年基準」を使います。
例えば運転資金や設備投資目的で銀行から借り入れを行います。
借入金の時点では通常の営業活動なのか長期的なものか判断が難しいです。
そこで一年基準で判断します。
返済期限が決算日翌日から1年以内であれば流動負債の「短期借入金」に分類されます。
1年を超える返済期限であれば固定負債の「長期借入金」に分類されます。
貸借対照表の順番は「流動性配列法」
貸借対照表にはいろんな「勘定科目」があります。
これはどのように並べるのでしょうか?

これにもルールがあります。
それが「流動性配列法」です。
流動性配列法とは「資産の部と負債の部は現金化しやすいものから記載すること」です。
流動性とは「現金化しやすい」ということです。
通常であれば
「資産の部は」
- 現金預金
- 受取手形
- 売掛金
- 有価証券
- 棚卸資産
「負債の部」は
- 支払手形
- 買掛金
- 短期借入金
といった順番になっています。
このルールは「そんな感じなのね」ってぐらいで結構です。
最後に
今回は貸借対照表のルールについて解説しました。
実務においては覚えてもほとんど役に立ちません(^^;)
ただどのようなルールで流動と固定が分類されていることや、勘定科目の順番などはちょっと気になるところです。
私は勉強し始めの時にそのように思っていたので、今回書くことにしました。
今回は深堀せずに、サラッと流す感じにしてください(^^)
次回は損益計算書について解説したいと思います。
できるだけ早く記事をアップしていきますので、また読んでやって下さい!