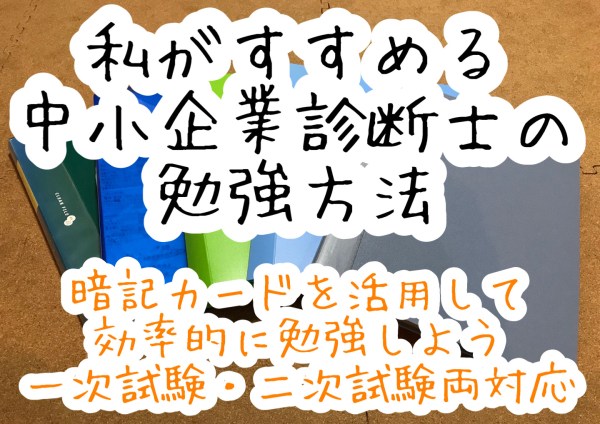こんにちは!中小企業診断士のカズユキです。
私は組織を変えるために5S活動をおすすめしています。
「5S活動とは何じゃ?」と思った方は下記ブログ内容を参考にしてください。
守りやすいルールを作ろう
5S活動を成功させるには決めたことをルールを守らせる必要があります。
5S活動によってせっかくきれいになった職場や工場が元に戻ってしまうと、また同じ労力を使って片付けなければなりません。
つまり活動後は「維持」する必要があります。
しかし単にルールを守らせるだけでは足りません。
例えば、ルールを守ると凄く手間がかかったり、面倒だったりするとどうでしょうか?
「いちいちこんなことやってられない!」
となってしまい、だんだん手を抜くことになってしまいます。
そうすると、徐々に乱れ始めます。
「ちゃんとルールを守らないと困る!」
と叱っても、
「こんなルール守っていたら仕事にならない!」
とケンカになってしまうこともあります。
更にとどめの言葉として
「上からやれと言われているから」
何て伝え方をすると、部下に納得させることはできません。
ではどうすればよいのでしょうか?
答えは「ルールが守られやすいように工夫をする」です。
つまり、面倒なことをしなくてもルールが守れるようにしておけば、メンバーも不満を言わずに自然に守ってくれます。
例えば、すぐに掃除がしやすいように道具を近くに置くようにします。
終了5分間は掃除をするというルールを決めた場合、近くに道具があるとストレスなく掃除をすることができます。
このように「手元化」をすることで、メンバーにルールを守ってもらえるようにします。
ルールを守らせることは大事ですが、ルールを作るほうも守りやすくする仕組みを作ることが大事です。
また人の心理を突いた方法で守らせるようにすることもできます。
それが今回のタイトルになる「ツァイガルニク効果」です。
ツァイガルニク効果とは
「ツァイガルニク効果」は、ツァイガルニクというソ連の心理学者が示した考え方です。
人は「中途半端なままで終わってしまったことについては、気になって仕方がない」という心の動きがあることを、実験で明らかにしました。
何となくわかりませんか?
私の場合は、一度掃除をやり始めたら細かいところまで気なってしまうので、どんどんやりたくなります。
それを5S活動に取り込むことで、きれいな状態を維持できる仕組みにします。
例えば下の写真は、5Sでよくある「形跡管理」というテクニックです。

形式管理というのは「道具の形を示すことで、どこになりが収まるかを管理する方法」です。
写真は机の一番上の引き出しを撮影したものです。
一つだけ道具が収まっていないことがわかります。
ここに電卓が収まっているのですが、形式管理をすることで何が引き出しの中に入っていないかがすぐにわかります。
この状態になると「全部おさまっていないので、なんかイヤだな」って気持ちにさせてくれます。
そして、
「どこにいったんだろう?」
「戻さなきゃ」
という衝動にかられます。
これがツァイガルニク効果です。
5Sの整頓では、このような形式管理をすることで元に戻してもらえる仕組みを作ります。
写真のような場合は、スポンジやマットを切り抜いて作成します。
100均なんかで手に入るものを活用すれば、誰でも作成することができます。
他にも道具をテープで縁取りしたりして置場を明示します。
縁取りと道具の名前だけでなく、写真を貼っておくとわかりやすいですね(^^)
このようにあるべき姿を明らかにしていれば、それと乖離した状態が気になるようになり、自然と正しい場所へ置きたくなる、というわけです。
目的を説明して、気持ちの良い職場環境へ
今回は心理学を参考に5S活動の整頓を解説しました。
仕事の進め方をめぐって、ルールを作る側とルールを守る側で衝突が起こります。
その原因を探ると、情報共有が十分できていないことが挙げられます。
ルールを守る側からすると、きちんと目的も告げられずに「上からの命令」だけでは納得がいきません。
新しいルールがやりやすくなったとしても、あえて古いルールで突き通すような人もいます。
ルールを作る側から見れば、
「どうして守らないんだ!」
「うちの会社は、命令を聞いてくれない」
といった気持ちになります。
また、命令を伝えればすぐに実行してもらえると思っています。
実際にはそれほど単純なことではありません。
ルールを浸透させるには、目的の共有化が重要です。
ルールを変えるということは、これまでのやり方に何か問題があったということです。
それを説明して、次にそれを克服するための新しいやり方を説明します。
その後も、新しいやり方が浸透しているかどうかをパトロール等でチェックしなければなりません。
新しいルールを職場で浸透させるには、根気が必要です。
ある会社では作業標準書の変更を浸透させるに数か月を要しました。
ベテランになってくるほど、従来の作業に慣れているため、なかなか変更に応じてくれません。
そんな中、現場のリーダーは丁寧に目的を説明することで、浸透させることができました。
組織の文化を変えることは簡単ではありませんが、守りやすいルールを構築すれば、みんながハッピーになります(^^)
ちなみに中小企業診断士の勉強では、組織論やモチベーション理論といったことを学ぶことができます。
このブログでも、いろんな理論について解説しています。
知識を持って物事に取り組めば、より精度の高い仕事ができます。
いろんな経営に関する知識を身につけて、職場環境改善に取り組んでみてください!